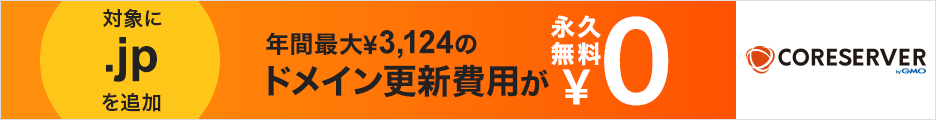「君はナポレオンになるんだ。」
出生後まもなく無呼吸発作になり救急搬送された彼は誰かに言われた気がした。
「まるで王様が囲いから出て人々に寄り添うように。」
山村信夫は山村家の長男として生まれた。
「次は、ちとせちょう」
それから20余年後、電停名を告げるアナウンスを聞くと、信夫は財布からICカードを取り出し、ズボンの右前ポケットに滑り込ませた。降りる寸前まで財布の中に入れておくと、降りるときにもし見つからなかったらどうしようと余計な心配を抱かなくて済むよう彼が決まってする癖である。かと言って専用のカードホルダーを持っているわけでもない。ポケットに片手を突っ込んだまま、彼の目線は窓の外の景色にあるが、右手はポケットの中のカードを握っている。このカードは元々東日本が本社の鉄道会社がつくったものだが、全国津々浦々の鉄道や市電など大半の公共交通機関で利用できるらしかった。
「まもなく、ちとせちょう」
信夫はゆっくりと座席を立ち前方へと向かったが、この電停で降りる乗客は彼しかいないようで他の誰も彼に追随する者は居ない。路面電車を降りると右手に灰色の建物が見えた。公共職業安定所は1階が求職検索ボックスや失業相談窓口、2階が再就職手当ならびに失業手当の給付窓口、3階が労働基準監督署となっており、1階では外国人向けの求職紹介サービスもおこなっているためか、信夫が待合席で待たされている間も彼の背中越しに通訳者と相対する利用者の激しい中国語が行き交っているのが聞こえてくる。
「ねえ、台湾一周してみない?」
かつての同僚で元カノから携帯にメッセージが入った。
「無理。俺、仕事クビになったから。」
と正直に返す。すぐに既読が付いたのを確認して、
「元気かい?」
と打つが、今度はなかなか既読が付かない。不安になって通話ボタンを押してみたが、応答はなかった。おそらくブロックしたのだろう。まあ、いいさ。所詮その程度の付き合いだったってことさ。声には出さず自分を励まそうとするが、振られたという事実と独りぼっちになったという現実が彼に重く覆いかぶさってくる。その重圧に耐えられず、公共職業安定所の外に出た彼は落ち葉で埋め尽くされた玄関の先に転がる一本の空き缶を蹴っ飛ばした。それは敷地の外の道路へ飛んでいったが、やがてそこまでたどり着くと手で拾い上げ顔の近くへ持って行き、上を向きながら口を開け無糖コーヒーのスチール缶から滴る液体を飲み込んだ。やけくそだったが、意外にもそれはのどの渇きを潤していく。
「へえー、案外いけるな。」
大学院を含め4年半の函館生活は信夫を人間的に大きく成長させた。
「香辛料は親水性がほとんどないから鶏がらスープを入れた後に入れるのはダメだよ。その分、油との相性がよいから最初に炒めるようにするんだ。」
寮生200人分のキーマカレーをつくるのは爽快だった。鶏がらとトマトベースのだしにカレーパウダーと材料も初めて使うものばかり。鶏がらスープひとつとっても、他に人参、玉ねぎ、セロリ、にんにく、しょうがを乱切りにして寸胴にぶちこんで鶏がらと一緒に一晩中弱火で煮込む。鶏がらは最初に血抜きをしなさいと信夫は仲間から注意された。血抜きとは、いったん鶏がらだけを数分間だけ沸騰させ、火を止めたあとで取り出した鶏がらの凝り固まった血のかたまりのような部分をすべて水道水で洗い流して、再びきれいな水で今度は人参、玉ねぎ、セロリ、にんにく、しょうがと食塩と一緒に煮込み始めるまでの一連の作業を指す。これをしないと、非常に料理としては提供できないほど臭みのある状態に仕上がってしまうという言うくらいだから、ものすごく重要な作業である。料理の旨みも去ることながら、ナポレオンと呼ばれるトランプゲームがこれがまた面白く夜が明けるまで他の仲間と熱中してしまい、大学の授業に寝坊する日々が続き、いくつかの単位を落とした。
「大丈夫、俺はナポレオンなんだから。」
全然大丈夫なことはなかった。信夫は大学1年目で留年した。
「ところで、山村は大学で何を勉強しに来たんだい?」
ふと自分より4つも年齢が上の者に聞かれた。
「僕は根っからの田舎者で、なおかつ身内からも疎まれるようなめっかち人間なので、ヤモリのようにブラブラひょろひょろとしたくて。」
あるとき外国で起きたフェリー事故に関する論文の一部を記事にしたいという連絡を出版社から受けた。一般的に事故原因とされる客室部の改装や過積載という内容ではなく、海外に引き渡される前段階で設計上の欠陥があったとも受け取れる論文を学会で発表したことに端を発する。彼は月刊雑誌「新大陸」編集部から送られてきたメールを1通り見終えると迷惑メールフォルダに移動した。彼の論文査読者でもあるゼミの教授からは、論文に関する取材は一切受けないよう固く言いつけられている。一歩間違えば国際問題にも発展しかねない問題と思われていた為、この件は教授の専権事項となっていた。実際、事故の翌日には研究室へ国内のテレビメディアが取材に来た。教授は記者たちに模型船と実験設備を見せたあと、学生たちに実験器具や模型等の後片付けを依頼し終えると、最後に記者に向かって告げた。
「今から言う内容は絶対に放送しないでください。もし電波にのせようものなら国内の造船企業が外国からのバッシングにあい、風評被害を受けるおそれがあります。」
その後、教授が記者に何を語ったのかは信夫の知るところではない。何せ、その間、自分は1作業者として模型船をホイストで吊り上げ所定の位置に戻したり、まわりの精密機器を片付けるのに夢中だったからである。その数日後、「新大陸」編集部から研究室宛てに1通の封書が届いた。中には返信用封筒と1万円札が10枚入っている。教授は困り果てた様子で、
「山村君、仕方ないから、事故を起こした供試船模型の写真を同封して返送してあげなさい。先日のメールを私も読みましたが、彼らは写真が欲しいのでしょう。」
彼はフェリー「つくし」の1/65サイズ模型の写真を机のパソコンからプリントアウトし、封筒に入れ、封をしようとした。
「あ、山村君、ついでにこれも。」
それは大学併設の曳航水槽で模型試験を行っている様子を撮った写真だった。水面に浮かぶ模型船が治工具によっておよそ20度のヒール角(船体傾斜角)をつけられ曳引電車に拘束されている。そして、その脇にはおそらく試験実施者であろう者の横顔が小さく映っていた。
月刊雑誌「新大陸」編集部のもとにとある男が訪ねてきた。
「フェリーに設計ミスがあった!?」
と書かれた記事の内容に感銘を受けたとのことであると。ぜひ情報提供者のお話を聞きたいと。その男は元刑事と言った。編集部の社員はその男に言った。
「情報提供者など最初から居ません。貴方は我々の書く記事が完全な創作であることを知らないのですか?あれはすべてでっちあげです。」
その男は、
「分かった。」
という様子で、重い口を開く。
「実は、記事に掲載されていた白黒写真のことでお話をうかがいたくて来たのです。できれば原本をお見せいただくことはできませんか?すぐお返ししますので。」
そう言われた社員は、
「あー写真ですか。それならよいですよ。」
と言い、模型実験の様子を映したカラー写真をその男に渡した。男は写真を受け取ると、しばらく凝視した後、目をつむる。
「あのー、どうかしましたか?すいません、もうよいですか?」
しびれを切らした社員が言った。
「あ、これはこれは失礼しました。つい、自分の世界に入ってしまいました。」
と男は言うと、写真を社員に返した。社員は怪訝な様子でその男に聞く。
「何かおかしなことでもありましたか?」
男は吹き出る汗をぬぐいながら答えた。その男の興味は真ん中に映る実験機器や模型船ではなく、端っこに映る小さなものにあった。「あ、いえ、いやーこの船はかっこ良いですね。」
と適当にうそをつく。今度は社員が返答に困った様子で
「この船は私の息子が趣味で買ったプラモデルなんですよ。いや本当に困ったものです。」
「ではありがとうございました。」男は「新大陸」編集部を後にした。
男は地元の警察官を途中で退職し、今は占い師の傍ら公園の清掃アルバイトで生計を立てていた。占い師と言うがいわば霊能者である。しかし、そちらのほうの稼ぎは乏しく、何か突破口を掴みたかった。そのため、さきほどは情報提供者に会いたい等とつい本音が出てしまった。男はさきほどの写真の端にうつっていた人の横顔を見たとき、一瞬でひらめくものがあった。
「間違いない、水子霊が憑いている。」
男は自らが師と仰いだこともある作家の本を手に取る。
「水子霊は間違いなくこの世に存在する。妊娠して2か月経過すると、胎児にはもう霊が宿っている。そうなると、出産までの間に堕胎か流産をおこなった霊は水子霊となる。」
男は思った。
「この水子霊は流産したものではない。おそらく・・・」
信夫は小学2年の誕生日プレゼントに両親から天体望遠鏡を買ってもらった。寝台急行列車「はまなす」は車内の照明が暗めに設定されているから、ターミナル駅を出発する列車の左側の車窓にはこの町の裏夜景が広がる。
「俺は、はまなすが好きだ。」